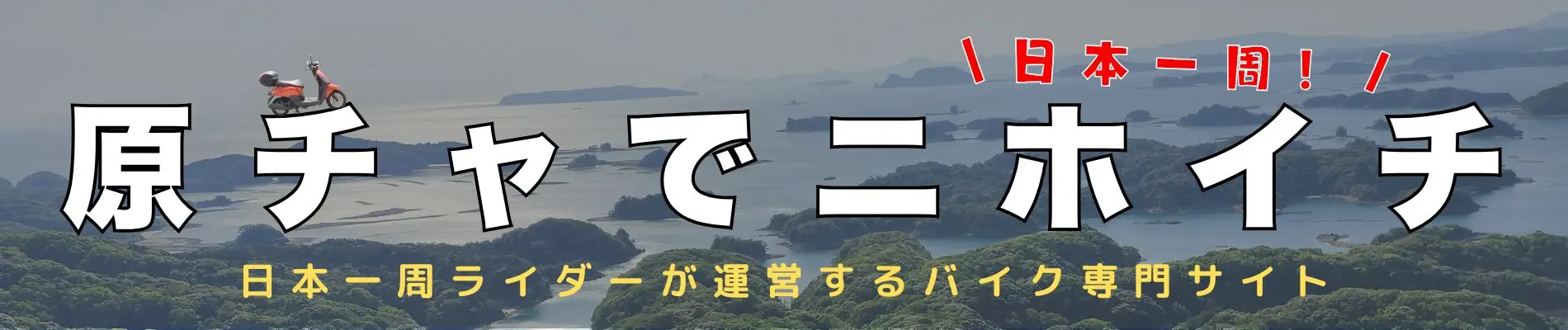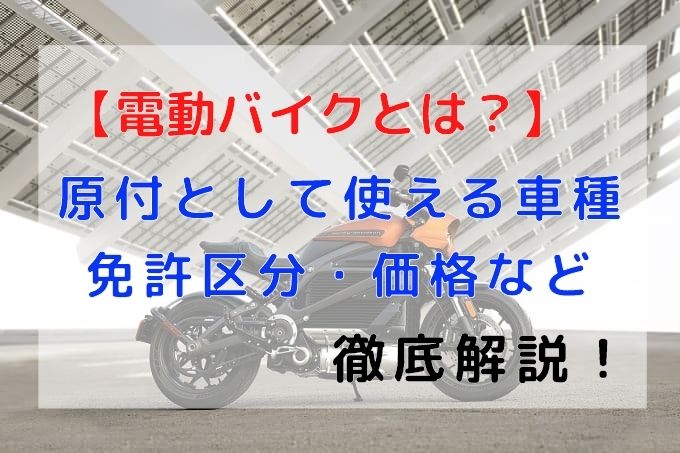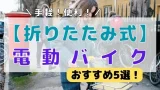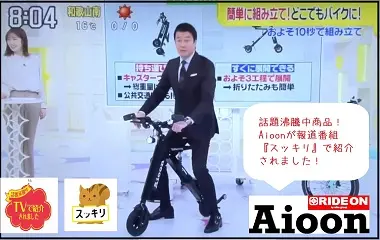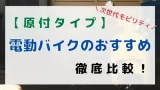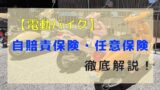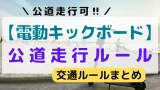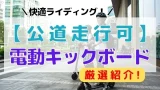~本記事で解決する悩み~
- 最近よく聞くようになった電動(ev)バイクとは?
- 電動バイクの車種や価格はどんな感じ?
- 電動バイクって原付として使えるの?

電動バイクって最近よく聞くよな!
テレビでも乗ってるの観るし、おれも乗ってみたいな。
詳しく教えてくれよ。

OK!
じゃあ今回は、電動バイクについて解説するよ!
電動バイクの車種や免許、価格の目安など、基礎的なことを紹介していくね!
本記事は、電動バイクに興味のある方向け記事です。
テレビ番組でも、「電動スクーターでトコトコ旅をする」というのが流行っていますが、最近は電動バイクに興味を持つ方も多いのではないでしょうか?
これからの時代、乗り物は電動に変わっていくことが予想されます。
本記事では、そんな電動バイクについて、原付歴15年&超ロングツーリングも数こなしてきた原付ヘビーユーザーの僕が、電動スクーターを徹底解説します!
本記事をお読みいただくことで、「電動バイクについての基礎知識」が身に付き、これから電動バイクデビューするときのハードルも下がるかと思います。
ぜひ最後までお読みいただき、次世代乗り物を先取りしていきましょう!
(※本記事は、2021年4月5日現在の情報で作成しています。)
電動バイクとは?

’https://www.yamaha-motor.co.jp/’
電動バイクとは、その名のとおり「電気」で動くバイクのことです。
通常は、ガソリン燃料でエンジンを動かして走行しますが、電動バイクの場合、充電したバッテリーからモーターへの出力となり、モーター動力を使って走ります。
近年、環境問題への対応として「排ガス規制」が進む中、電動の乗り物は注目を浴びてきており、電動バイクも同様に次世代を担う乗り物として期待されます。
電動バイクのメリット・デメリットは?
環境でのメリットはありますが、ユーザーにもメリットがある乗り物となります。
反対にデメリットとなる面もありますので、以下にそれぞれ紹介します。
~メリット~
- ランニングコストが安い!
- 電気代(燃費良い)
- メンテナンスコスト
- 家庭用コンセントで手軽に充電できる!
- 騒音・振動が少ない!
~デメリット~
- 1回の充電での走行距離が短い!
- 充電にかかる時間が長い!
- イニシャルコスト(本体とバッテリーの値段)がやや高い!
電動バイクの定格出力って?
電動バイクのスペックや仕様をみていると、「定格出力」という単語が出てきます。
ガソリン車に乗っていると、なかなか馴染みのない言葉かもしれません。
定格出力とは、ガソリン車でいう排気量(cc)のことです。
定格出力が大きい
⇒出力パワーが大きく、速度が速くなる
ざっくりと、こんな感じに思っておくとよいでしょう。
その結果、ガソリン車の排気量ごとでの免許区分等があるように、電動バイクにも車両や免許の区分も変わっていくことになります。
車両区分については、後に詳しく紹介していきます。
電動バイクの価格は?
電動バイクの価格は、ガソリン車よりもやや高い印象を受けます。
たとえば、バイクメーカーヤマハの原付「Vino」は、EVタイプも出ており、
- Vino(原付のガソリン車)
⇒メーカー希望小売価格:214,500円(税込) - E-Vino(原付一種の電動バイク)
⇒メーカー希望小売価格314,600円(税込)
と、メーカー希望小売価格を比較すると、やや高めの設定です。
【電動バイク】車種・価格の目安!
現在、国内市場に出ている電動バイクと言うと、原付タイプが多い傾向です。
たとえば、次のような車種!
- E-Vino(ヤマハ)
- Aioon(RIDE ON)
- その他リース向け等の電動バイク(ホンダ)
詳しく見ていきましょう!
E-Vino(ヤマハ)

“ヤマハHP”
「E-Vino」は、「某テレビ番組(充電バイク)」でも有名となっている電動バイクです。
原付一種タイプで、有名バイクメーカーの車種であるヤマハ「Vino」の電動版となっています。
レトロポップでおしゃれなスクーターですよね!
車両重量68kgと軽量ボディで取り回しが楽ちん!
充電満タンでの航続距離は約29kmですが、別売りのスペアバッテリーを使用することもできます。
バッテリー重量は6kgなので、充電操作もやりやすいです。
E-Vinoは、電動バイクで30万円を切る値段なので、割と手ごろに買える車種かと思います。
~特徴~
- メーカー希望小売価格(10%税込)
314,600円 - 定格出力
0.58kW(原付一種) - 1充電走行距離
32km(30km/h定地走行テスト値) - 1回の充電あたりの電気代
約14円(※参考) - 充電時間
約3時間 - その他
- 見やすく分かりやすいデジタル液晶メーター
- BOOST機能
⇒加速したいとき、登坂などで一時的にパワーUPする機能搭載 - 走行状況に応じて「標準モード」「パワーモード」切り替え可能
Aioon(RIDE ON) ⇒おすすめ!
先着50台限定!18,000円OFF中!
※詳細は公式サイト≫Aioon
Aioonは、簡単に折りたためる電動バイク。
折りたたみ時のサイズは、L106×W50×H36cmとコンパクトで、車に積んで持ち運ぶなども容易で、「旅先でツーリング」なんかも可能です。

”Aioon
折りたたみ時には、引いて移動できるキャスター付きのため、通勤・通学等でも使い勝手は良いでしょう!
デメリットとなる点は、最高速度が約25km/hの設計となっておりやや遅めなところ。
交通量の多い道・上り坂などは、走りにくさは感じるかもしれません。
自転車代わりに乗るような感じで、
- ちょっとした買い物
- 気分転換のライディング
- 旅先での移動手段(観光地まわり)
- 通学・通勤等で駅までの移動手段
など、ライディングシーンを選んで楽しむと良いですね!
スマートデザインで、つい乗りたくなるスタイルのAioon。
1台あると生活の楽しみが増えるでしょう!
~特徴(原付一種タイプ)~
- メーカー希望小売価格(10%税込)
156,000円 - 定格出力
0.36kW原付一種 - 最高速度
約25km/h
※登坂能力8~20度 - 航続距離(1充電走行距離)
約30km - 充電時間
約4~5時間(約3時間で80%) - 車体重量
約16.5kg
※バッテリー約1.7kg - 折りたたみ可能
- 展開時サイズ
L110×W50×H85cm - 折りたたみ時サイズ
L106×W50×H36cm
- 展開時サイズ
- 保証
- バッテリー保証1年間
- その他
- 折りたたみ時にキャスター付き
- 前後ディスクブレーキで制動性が高い
- 100kg以上の不可を5万回の疲労試験合格
Amazonなどの通販より、公式サイトでのキャンペーン購入で安く買えるときがあるのでチェックしておきましょう!
(※台数限定)
▼Aioonの詳細&購入はこちら!(公式HP)
(参考)通販購入はこちら!
その他有名バイクメーカーの電動バイク
他にも、有名バイクメーカーでいうと以下のものなどがあります。
- PCX ELECTRIC(ホンダ)
- 定格出力0.98kW(原二タイプ)。
- リース専用。
- ベンリィe:Ⅰ(ホンダ)
- 定格出力0.58kW(原一タイプ)。
- 法人向け。
- 値段:税込737,000円
- ベンリィe:Ⅱ(ホンダ)
- 定格出力0.98kW(原二タイプ)。
- 法人向け。
- 値段:税込737,000円
- ジャイロe:(ホンダ)
- 定格出力0.58kW(原一タイプ)。
- 法人向け。
- 値段:税込550,000円
これらは、リースまたは法人向けのタイプとなりますが、値段はまあまあ高額になりますね!
その他にも、電動バイク市場は、国内メーカーだけでなく海外メーカーも参入してきています。
これからもまだまだステキな電動バイクが出てくることが期待できますね!
▼電動バイク(原付タイプ)のおすすめ紹介はこちら!
電動バイクの車両区分と免許区分は?

では、電動バイクの車両区分についてみていきましょう!
まず、車両の区分として「道路交通法」によるものと、「道路運送車両法」によるものに分かれます。

なんか難しそうだな・・・。
少しややこしいのですが、ざっくりと「免許・交通ルール・税金・車検の要不要など」といった点を、法律上で定めていると覚えておくとよいでしょう!
電動バイクの車両区分と免許区分

まず、電動バイクを運転するための免許について!
以下のとおり、定格出力によって必要な免許が分かれています。
- 0.6kW以下
⇒原付免許 - 0.6kW超~1.0kW以下
⇒小型限定普通二輪車免許 - 1.0kW超~20kW以下
⇒普通自動二輪車免許 - 20kW超
⇒大型自動二輪車免許
定格出力1.0kW以下の二輪車がいわゆる「原付」と呼ばれるもので、0.6kW以下が原付一種、0.6kW超~1.0kW以下が原付二種となっています。
二輪車の区分を以下の表にまとめます!
| 電動バイク (定格出力) | (参考) ガソリン車 | 車両区分 | 必要な免許の種類 |
|---|---|---|---|
| 0.6kW以下 | 原付第一種 0~50cc | 原動機付自転車(原付) | 原動機付自転車免許 |
| 0.6kW超~ 1.0kW以下 | 原付第二種 ~125cc | 普通自動二輪車(普通二輪) | 普通自動二輪車免許 (小型限定) |
| 1.0kW超~ 20kW以下 | 軽二輪 ~250cc | 普通自動二輪車(普通二輪) | 普通自動二輪車免許 (普通二輪免許) |
| 1.0kW超~ 20kW以下 | 小型二輪 ~400cc | 普通自動二輪車(普通二輪) | 普通自動二輪車免許 (普通二輪免許) |
| 20kW超~ | 小型二輪 400cc~ | 大型自動二輪車(大型二輪) | 大型自動二輪車免許 (大型二輪免許) |
上の区分では免許の種類として分けていませんが、区分によってAT限定免許ならMTの電動バイクは運転できません。
MT車に乗りたい方は注意しましょう。
また、その他電動バイクの運転で気になりそうなルールとして、
- 二人乗り(タンデム走行)⇒0.6kW以上
(※二段階右折も原二と同様の位置づけ) - 高速道路⇒1.0kW超~
のバイク区分になります。
二輪の区分についての関係法令(抜粋)を以下に載せておきますので、興味のある方はご参考にください!
道路交通法施行規則(抜粋)
(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
引用:道路交通法施行規則
第一条の二 二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし、・・・
(自動車の種類)
第二条
大型自動二輪車 総排気量が〇・四〇〇リットルを超え、又は定格出力が二〇・〇〇キロワットを超える原動機を有する二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、・・・
普通自動二輪車 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの
道路運送車両法施行規則(抜粋)
(原動機付自転車の範囲及び種別)
引用:道路交通法施行規則
第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
電動バイクに車検は必要?

原付クラスの電動バイクであれば、車検は不要になります。
ガソリン車の場合、250cc超の小型二輪からは車検が必要です。
電動バイクの場合は、現状、定格出力での車検に関する規定はないため、
「長さ2.5m×幅1.3m×高さ2m以下」
なら車検は不要となってます。
(※陸運局より)
これだけ大きなサイズの電動バイクはほとんど出回っていない?かと思いますので、基本は不要かなと思います。
ちなみに、ガソリン車の場合は250cc超から車検が必要となっていますが、250cc未満でも上のサイズを超える場合は車検が必要になります。
【電動バイクの維持費用】原付クラスの軽自動車税や自賠責保険は?

電動バイクを所有すると、原付と同様に税金・自賠責保険料といった費用は必須でかかってきます。
軽自動車税は?

毎年4月1日時点でバイクの登録があると、区分に応じて軽自動車税がかかります。
電動バイク(原付クラス)の所有で発生する定格出力ごとの軽自動車税については、下表のとおりです。
| 電動バイク (定格出力) | (参考) ガソリン車 | 軽自動車税 |
|---|---|---|
| 0.6kW以下 | 原付第一種 0~50cc | 2,000円 |
| 0.6kW超~ 0.8kW以下 | 原付第二種 50cc超~ 90cc | 2,000円 |
| 0.8kW超~ 1.0kW以下 | 原付第二種 90cc超~ 125cc | 2,400円 |
(※参考:東京都日の出町HP)
これらは、各市町村の自治体に申請してナンバープレートの登録をします。
定格出力1kW超の電動バイクとなると、陸運局にて手続きを行うことになり、軽自動車税のほかに重量税もかかってくることになります。
自賠責保険は?

自賠責保険については、保険期間によって金額が異なり、長期契約するほどお得に加入できるようになっています。
| 保険期間 | 自賠責保険料 (1.0kW以下) (125cc以下) |
|---|---|
| 12か月 | 7,070円 |
| 24か月 | 8,850円 |
| 36か月 | 10,590円 |
| 48か月 | 12,300円 |
| 60か月 | 13,980円 |
自賠責保険は、「原付の自賠責保険を取り扱っている保険会社」か「コンビニ」で加入手続きをしましょう!
どこで加入しても、保険料・補償は変わりません。
コンビニなら24時間365日、簡単に加入できちゃうので楽ちんですね!

保険加入したらステッカーがもらえるので、ナンバープレートに貼り付けることと、加入時に発行される「自賠責保険証明書」を常に携帯(運転時)するようにしましょう!
原付として電動バイクを運転する場合って任意保険は必要?

任意保険については、その名のとおり「任意」での加入となります。
「そもそも任意保険なんて必要なの?」「自賠責だけでよいのでは?」と考える方は多いかと思いますが、この疑問に対してお答えするならば、「できれば加入した方がよい!」と考えます。
下表にて、自賠責と任意保険の保険内容を比較してみましょう。
(※任意保険の保険内容については参考。保険会社・プランによって異なる。)
| 保険内容 | 自賠責保険 | 任意保険 |
|---|---|---|
| 対人賠償保険 | 〇 ※上限あり | 〇 ※無制限 |
| 対物賠償保険 | ✕ | 〇 ※無制限 |
| 自損事故保険 | ✕ | △ |
| 人身傷害保険 | ✕ | △ |
| 搭乗者傷害保険 | ✕ | △ |
| 無保険車障害保険 | ✕ | △ |
| ロードサービス | ✕ | △ |
補償内容が全然違いますよね!
繰り返しになりますが、自賠責保険は、被害者救済のための最低限の補償となっており、「対人賠償」のみです。
自分への損害や、相手車両、建物への損傷があったときには補償対象外ですし、唯一ある対人賠償についても次のように上限があります。
~自賠責保険の補償~
- 死亡事故・・・3,000万円
- 後遺障害・・・3,000万円
※神経系統に著しい障害を残して、常時介護が必要な場合は4,000万円まで - 障害による損害(治療が必要な場合)・・・120万円
ただ、電動バイクを原付クラスとして乗るなら、「手軽感」な乗り物というイメージがあり、そこまで保険の必要性を感じないかと思います。
しかし、一度想像してみましょう。
- もし、運転中に車にぶつけてしまい、自分が転倒してケガしたら・・・
- 相手車両をキズつけてしまったら・・・
- 自分の電動バイクを追い抜いていく車と接触したら・・・
- 通行人や自転車とぶつかって、相手をケガをさせてしまったら・・・

ちょっとした物損ならまだ数万~数十万円レベルの支払いで済むかもしれませんが、それなりの補償をしなければなりません。
さらには、自分がケガをしてしまったり、相手が大ケガまたは死亡事故となってしまった際には、自賠責保険だけでは、十分な補償を得られない場合が多々あります。

とは言っても、ネックは保険料ですよね!
「任意保険に加入するといっても、高いんでしょ?」という方は、インズウェブでできる任意保険一括見積もり(≫インズウェブ(バイク保険一括見積もり))という無料サービスがありますので、利用してみるとおもしろいです。
自分が乗っている原付やバイクなどの簡単な情報を入力するだけで、いくつかの保険会社の見積もりを一括して取ってくれますので、ぜひ試してみましょう!
「任意保険って実際のところいくらするの?」という方は多いと思いますので、大変便利なサービスです。
こういったお得な無料サービスは試してみなきゃ損ですよね!
▼無料一括見積もりはこちらから!
電動バイクの自賠責保険や任意保険については、下記事でも詳しく解説していますので、興味のある方はぜひご参考にください。
まとめ
「電動バイクとは」について、車種・免許・価格など、基礎的なことを解説しました。
次世代乗り物として注目されてきていますが、環境問題への対応から、電動バイクへの切り替えはマストになってきます。
電動バイクの知識を今から取り入れて、次世代乗り物を先取りしていきましょう!
▼電動の次世代乗り物!電動キックボードについて!
▼電動キックボードのおすすめ!