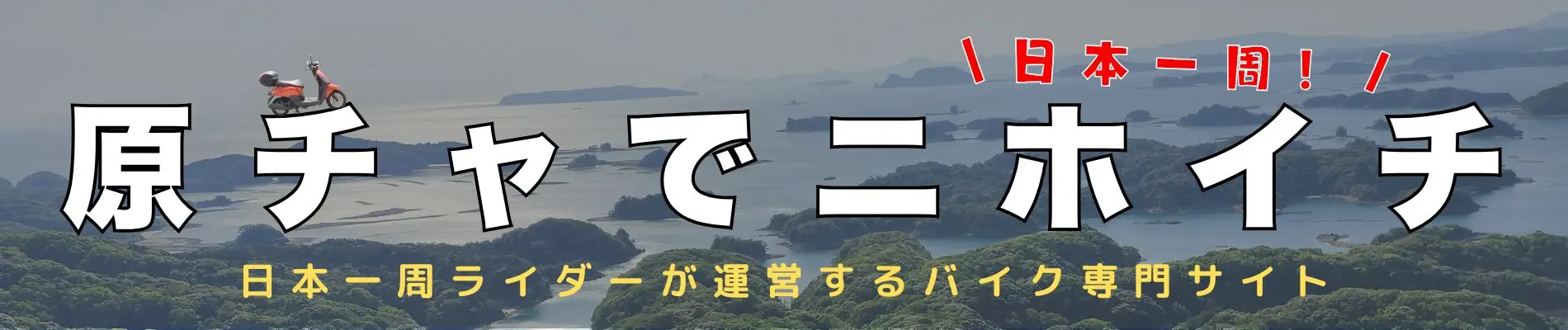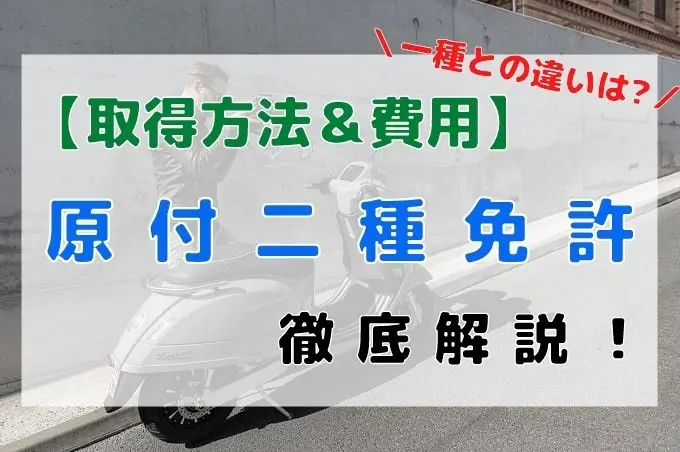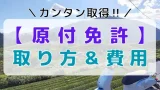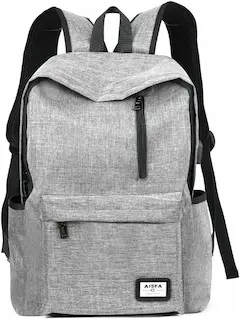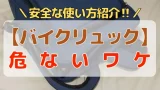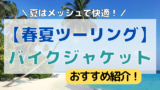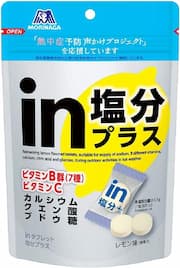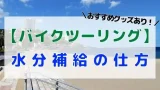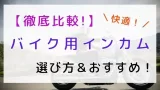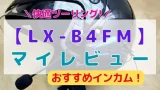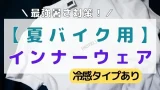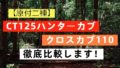~本記事のテーマ~
- 原付一種と二種の違いは?
- 原付二種免許の取り方は?
- 原付二種免許の取得費用は?

原付二種免許ってどうやって取るの?
一種と二種の違いがよくわからないけど、詳しく教えてくれよ!

OK!
じゃあ今回は、【原付一種と二種の違い・原付二種免許の取得方法や費用】を紹介するよ!
免許取得の難易度が上がる原付二種の取り方も詳しく解説するから、ぜひ参考にしてね!
原付二種免許は、正式には「普通自動二輪免許小型限定」。
二輪免許となるため、「原付」(二種)と言えど、~50ccの原付とは以下の点で大きく異なります。
- 排気量
- 免許
- 交通ルール
- 税金等費用面
原付と言えば、法定速度が30km/hなどといった独自の交通ルールがあり、自転車の延長のような形で乗る方もいるでしょう。
こういった一般的なイメージの「原付」は、原付一種のこと。
原付二種になると、制限も少なくなり、車に近い扱いとされて利便性が大きく向上します。
本記事では、そんな原付二種について、「一種との違い」や「免許の取り方・費用」を徹底解説します。
「スピードの出るバイクに乗りたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください!
▼二輪免許と運転可能なバイク
~バイクは雨対策必須~
バイク・原付用におすすめのレイングッズ!
\通販ならレインウェアも豊富!/
原付一種と二種の違いを徹底解説!

まずは、原付一種と二種の違いについて紹介していきます。
先にも述べたとおり、原付一種と二種では、以下の点で大きく異なります。
- 排気量
- 免許
- 交通ルール
- 税金等費用面
それぞれの違いについて、詳しくみていきましょう!
排気量

根本的な違いとして原付一種と二種では排気量が異なります。
- 原付一種・・・~50cc以下
- 原付二種・・・50cc超~125cc以下
排気量の違いにより、見た目はコンパクトでもパワーが大きく上がります。
以下でも紹介しますが、原付一種にあった交通ルール「法定速度30km/h」の制限がなくなり、スピードも上がります。
そのため、行動の幅は一気に広がるでしょう。
免許
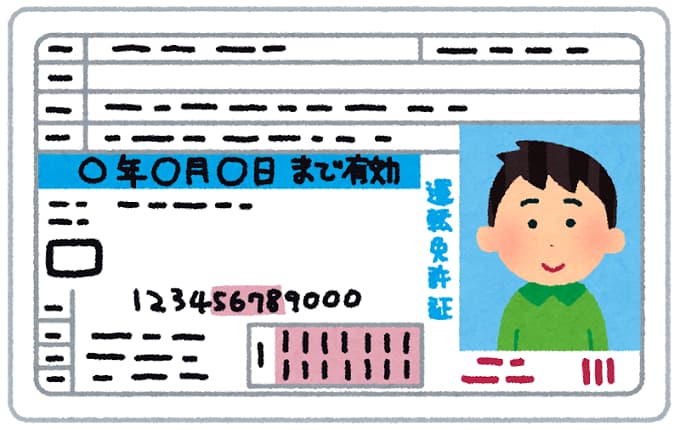
原付一種と二種で大きく異なるのが、免許が違うことです。
原付一種は、自動車免許や原付免許があれば運転できますが、二種の場合は二輪用の免許が必要です。
それぞれの必要な免許を次にまとめます。
- 原付一種:普通自動車免許または原付免許
- 原付二種:小型限定普通二輪免許
原付一種の運転に必要な「普通自動車免許」は取得する方が多いですし、持っていない方でも、原付免許なら比較的簡単に取得することができます。
一方、原付二種で必要な「小型限定普通二輪免許」は、厳しい実技試験もあるため、車の免許を持っている方でも教習所に通って取得する方が多くなります。
交通ルール
先にも少し触れましたが、原付一種と二種では、交通ルールが大きく異なってきます。
原付二種では、交通ルール上、ほぼ車と変わらなくなるため、利便性は上がりますが危険性も増します。
二種免許取得にチャレンジしようと思う方は、この違いを十分に理解しておきましょう。
それぞれの交通ルールの違いは次のとおり!
~原付一種と二種の違い~
- ナンバー
- 原付一種(50cc以下):白ナンバー
- 原付二種(50cc超~90cc):黄色ナンバー
- 原付二種(90cc超~125cc):ピンクナンバー
- 法定速度
- 原付一種:30km/h
- 原付二種:60km/h
- 通行車線の制限
- 原付一種:左側車線を通行
- 原付二種:なし
- 二段階右折の有無
- 原付一種:二段階右折
- 原付二種:なし
- 駐車場所
- 原付一種:「駐輪場」でOK
- 原付二種:は制限されるところも。正式には「駐車場」へ停める。
- 乗車人数
- 原付一種:乗車定員は1名
- 原付二種:2人乗り(タンデム走行)が可能となる。
※小型限定普通二輪免許以上の二輪免許を取得して1年以上経過後であったり、同乗車用ステップがあるものなどの条件はあり。
- その他
⇒原付一種・二種ともに、高速道路や自動車専用道路の通行はNG。
以上のような違いがあります。
原付二種になると「できること」がかなり増え、行動の幅は大きく広がります!
税金等費用面

では、原付一種と二種の税金等の費用面を見ていきましょう。
原付にかかる税金は次のとおりです。
~軽自動車税~
- 50cc以下(白ナンバー)
⇒年間2,000円 - 50cc超~90cc(黄色ナンバー)
⇒年間2,000円 - 90cc超~125cc(ピンクナンバー)
⇒年間2,400円
※自動車重量税は、125cc以下は非課税。
あと、自賠責保険は、原付一種と二種は同額の年額7,060円(複数年契約で割安になる)です。
任意保険の場合も、125cc以下は取り扱いが同じになるところが多いと思いますが、自動車の保険に加入している方なら、「原付特約」等の対象になってくる保険会社もあります。
お得に加入できる可能性もあるので、確認してみるとよいかと思います。

ライダーの方で任意保険に加入していない人は多いですよね。
じつは、万が一の事故の際、自賠責だけだと危険なんです。
(※自賠責⇒「対人賠償のみ」「最低限の補償のみ」)
インズウェブの一括見積もりなら、無料で保険料の最安値がカンタンに把握できます!
まずは、保険料をチェックしてみて、加入を検討しておくことをオススメします。

任意保険加入中の方も、安い保険が見つかるのでぜひお試ししてみてください!(無料で見積もり比較)
【原付二種】運転に必要な免許は?

繰り返しになりますが、排気量が50cc以下を原付一種、50cc超~125cc以下を原付二種と分けられます。
二輪車の排気量ごとの区分を一度まとめておきましょう!
| 車両分類 排気量 | 車両区分 | 必要な免許の種類 |
|---|---|---|
| 原付第一種 0~50cc | 原動機付自転車(原付) | 原動機付自転車免許 |
| 原付第二種 ~125cc | 普通自動二輪車(普通二輪) | 普通自動二輪車免許 (小型限定) |
| 軽二輪 ~250cc | 普通自動二輪車(普通二輪) | 普通自動二輪車免許 (普通二輪免許) |
| 小型二輪 ~400cc | 普通自動二輪車(普通二輪) | 普通自動二輪車免許 (普通二輪免許) |
| 小型二輪 400cc~ | 大型自動二輪車(大型二輪) | 大型自動二輪車免許 (大型二輪免許) |
先にも少し触れましたが、原付二種(50cc超~125cc)を運転するためには、小型限定普通自動二輪免許が必要になります。
さらに、オートマチックトランスミッション(AT)のみ乗れるAT限定免許もあります。
| 乗りたい原付 | 必要免許 |
|---|---|
| 50cc以下 | 原付免許 |
| 50cc超~125cc以下 | 小型限定普通二輪免許 |
| 50cc超~125cc以下 ※AT車のみ | AT小型限定普通二輪免許 |
AT限定の方が難易度は下がりますが、必要に応じて免許取得を行っていきましょう!
\通販で人気リュックを探す!/
原付二種免許の取り方は?

では、原付二種免許の取り方を紹介していきます。
原付二種試験の概要
まず、50cc超~125cc以下の原付二種免許取得の要件は次のとおり!
- 年齢は16歳から
- 住民登録がある都道府県の試験場で免許試験を受けること
試験内容は、
- 学科試験⇒普通自動車免許等を持っている人は免除!
※原付免許(一種)のみの方は受験必要! - 技能試験
- 適性試験
となっています。
原付二種免許の取り方
普通自動車免許を持っている方でも、おそらく自動車学校や教習所に行って免許を取得する方がほとんどでしょう。
ただし、原付二種の免許では、
- 「直接試験を受けて取得する方法」
- 「教習所に通って取得する方法」
の2通りの方法があります。
次に詳しくまとめます。
- 直接試験を受ける方法
⇒直接試験場で、適性検査・学科試験・技能試験を受験。現状の合格率は低い。
※普通自動車免許所有者は、学科試験が免除(原付免許のみなら学科試験は必要)。
- 指定教習所に通って取得する方法
⇒教習所で教習を受けて卒業検定を合格したあとに、適性検査・学科試験を受験。現状、この方法が主流となっている。
※この方法は技能試験が免除。普通自動車免許所有者は、学科試験も免除。
※指定教習所でない非公認の教習所の場合は、技能試験を受ける必要があるので注意する。
自動車免許を取るときもそうですが、自動車学校などに通って免許を取得する方が多いかと思います。
原付二種においても指定教習所に通って取得する方法が取りやすいようです。
~夏のツーリングに快適なジャケット~
\通販で人気ウェアを探す!/
原付二種免許の取得費用は?

原付二種免許を取得する場合には、次の手数料がかかります。
(※2020年9月27日現在)
~試験関連の手数料~
- 受験手数料2,600円
- 車両使用料1,450円
~取得時の費用~
- 普通二輪車講習12,000円
- 応急救護処置講習4,200円
- 交付手数料2,050円
⇒合計22,300円
※取得している免許等によって、免除されるものもある。
※不合格になると、受験手数料2,600円、車両使用料1,450円が都度必要となる。
取得にかかる費用は以上のとおりとなりますが、指定教習所を利用する場合には教習費用がかかることになります。
次に詳しく解説します。
~夏のツーリングは水分補給にも注意~
水分補給アイテムを携行して、健康かつ快適にツーリングを楽しもう!
原付二種免許取得で指定教習所を利用する場合について

原付二種免許を指定教習所に通って取得する人は多く、一般的にはこの方法を取るようです。
この場合、教習費用がかかり、直接受ける場合に比べ高額になります。
指定教習所を利用する場合のメリット、デメリットは次のとおりです。
~メリット~
- 技能試験が免除される。
~デメリット~
- 教習費用がかかる。
⇒地域にもよるが15~20万円程度。普通免許を持っていれば10万円程度。
※AT限定なら1~2万円安くなる傾向。 - 教習に何日か通わなければならない。
- 普通自動車免許なしの場合
⇒小型限定:学科教習26時間、技能教習12時間(AT限定なら9時間)必要。 - 普通自動車免許所有者の場合
⇒学科教習1時間、技能教習10時間(AT限定なら8時間)のみになる。
- 普通自動車免許なしの場合
指定教習所に通うことで、厳しい技能試験を免除されることが最大のメリットとなりますが、費用面と教習へ通う手間がデメリットとなります。
ただ、2018年に道路交通法施行規則が見直され、1日に受けられる技能講習が3時間⇒4時間に変更されています。
これにより、AT小型限定では最短2日間で修了できるなど従来より負担は減少しており、取得しやすくなっているようです。
▼インカムでツーリングがもっと快適に!

インカムがあれば、ツーリング中の「仲間との会話」や「音楽試聴」が可能!
より快適なツーリングが楽しめます!
※インカムデビューはコスパ抜群のB4FMがおすすめ!
(僕も愛用中!)
まとめ

原付一種と二種の違いや、原付二種免許の取り方・費用について解説しました。
少し複雑で分かりにくかったと思いますので、次のまとめます!
▼原付一種と二種の違い
| 項目 | 原付一種 | 原付二種 |
|---|---|---|
| 排気量 | ~50cc | 50cc超~125cc |
| 必要免許 | 普通自動車免許 または原付免許 | 小型限定普通二輪免許 |
| ナンバー | 白 | 50cc超~90cc:黄色 90cc超~125cc:ピンク |
| 法定速度30km/h制限 | あり | 法定速度60km/h |
| 通行車線制限 | 左側通行 | なし |
| 二段階右折制限 | あり | なし |
| 駐車場所 | 駐輪場 | 一部駐輪場では制限あり。 正式には駐車場へ停める。 |
| 乗車人数 | 1名 | 2人乗り可能 ※条件あり |
| 高速・自動車専用道 | NG | NG |
| 軽自動車税 (年額) | 2,000円 | 50cc超~90cc:2,000円 90cc超~125cc:2,400円 |
| 自動車重量税 | 非課税 | 非課税 |
| 自賠責保険 | 年間7,060円 (複数年契約で割安) | 年間7,060円 (複数年契約で割安) |
| 任意保険 | 単独の保険 or 自動車保険の特約 | 単独の保険 or 自動車保険の特約 |
▼原付二種の免許取得について
(※下表費用欄の「試験等手数料」は、受験時点で持っている免許の有無などで変わる。詳細料金は、試験場等で確認するとよい。)
| 取得パターン | 普通自動車 免許等 | 試験科目 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 直接試験 | あり | 適性検査 技能試験 | ・試験等手数料 |
| 直接試験 | なし | 適性検査 学科試験 技能試験 | ・試験等手数料 |
| 指定教習所 | あり | 適性検査 | ・試験等手数料 ・教習所費用 ⇒10万円程度? |
| 指定教習所 | なし | 適性検査 学科試験 | ・試験等手数料 ・教習所費用 ⇒15~20万円程度? |
原付免許とは異なり、原付二種免許の取得には厳しい実技試験があるなどレベルは上がります。
しかし、原付二種の運転では、交通ルールの制限はほとんどがなくなり、ライディングの幅は広がります。
あなたのライディングスタイルにあわせて、原付二種免許の取得にチャレンジしていきましょう!
~夏のツーリングに快適なインナー~
\通販で人気インナーを探す!/
≫原付ツーリングの完全ガイド
(※ツーリングに興味があるならチェック)